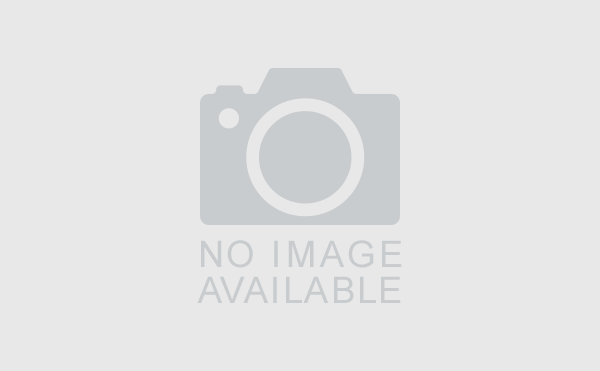未来への思考
昨年の春頃、友達と展覧会に行きました。場所は六本木近くの21_21 DESIGN SIGHTで、「2021年 Futures In-Sight」というテーマの展覧会でした。デザイナー、アーティスト、エンジニア、研究者、起業家、さらには学生など、さまざまな分野の人々が、彼らが100年後の世界について想像することを視覚的に展示しました。その名も「Future Compass」と題され、現在の行動や生産を検討し、未来を描くための視点としました。要するに、「未来についての思考」です。
展覧会を見終えて、最も直感的に感じたのは、面白い哲学の授業を受けたような感じでした。まず、異なる分野からの人々が、それぞれの立場や視点から未来を考えることがどれほど面白いかを体験できたことが興味深かったです。1つの仕事に長く取り組んだり、自分の研究分野にのみ没頭したりすることで、視野が狭くなり、考えが行き詰まることがあります。率直に言えば、私はしばらく自分の専門分野から離れ、インスピレーションを受け、新しい楽しみを見つけたいと思って展覧会に行っています。
展覧会の中で、極地建築家の村上祐資さんは、極地で生活する人々から学んだ未来へのアプローチについて語りました。「未来は変えられない。僕らが本当に変えられるのは過去だ」という立場です。「未来とは、過去という土に根を張り、生きていく姿勢から生まれるもの」です。彼は「科学とは時間を奪う学問だ。この一瞬の現象を、過去や未来を問わず、全ての時間に適用しようとする、再現性に依拠した、文字による秩序だ。対して歴史とは、いのちの目盛で刻まれる、人の営みの軌跡だ。歴史の繰り返しは、普遍性という時をかける観念をうむ。科学というせっかちな学問から恩恵を受けすぎている今日の僕らに、過去の上に根を下ろす力はまだ在るだろうか」と書いています。歴史は繰り返し、「普遍性」の概念を生み出します。
しかし、過去をどのように変えるのかは言及しませんでした。別の視点から考えれば、今日にとっては昨日が過去です。したがって、私が今日1冊の本を読み終えたい場合、昨日から行動を始め、夜遅くまで読書し、目標を達成することができます。このような「過去(昨日)」における非普遍性の行動は、過去を変える行動と呼ぶことができるかもしれません。そこで、私が今日その本を読み終えたことは、一般的な行動ではないと言えるでしょう。なぜなら、本を読むことは毎日のように繰り返されることではなく、毎日の普通の行動ではありません。その結果、私は「未来(今日)」を変えたと言えます。したがって、村上さんの「未来は変えられない」という見解に完全に同意するわけではありません。もちろん、彼が過去の重要性を強調していることを否定しません。実際、誰もがそれを否定できないでしょう。ある程度、「未来は過去にある」と言えるのは、未来を一部予測できるからです。しかし、未来の具体的な部分を予測することはできません。過去の経験や歴史の繰り返しにより、「人間は大自然を破壊することで最終的に大自然から報復を受ける」ということが理解できますが、新型コロナウイルスのようなものは予測できませんでした。つまり、過去から未来の方向を窺うことはできますが、未来を具体的に予測することはできません。
新型コロナウイルスが契機となり、多くの人々が未来への思考に熱中しました。しかし、我々が思考するかどうかにかかわらず、未来は確実にやってきます。では、なぜ私たちは未来を考え続けるのでしょうか?生命科学者の高橋祥子さんは、世界中には環境問題や貧困問題など、さまざまな社会問題が頻繁に発生しており、この状況は私たちの期待に添っていないことを指摘しました。私たちはこの「現在」が続くことを望んでいないので、未来には異なる要素があることを想像することがあります。しかし、反ユートピア的に見える世界では、現在の問題が解決されたとしても、新たな問題が次々に発生し、絶え間なく現れます。高橋さんは、唯一の希望は「我々が思考し、学習し、常に前進できる」という知性だと述べています。未来への思考を諦めない限り、無限の創造力を発揮し、美しい未来を創り出すことができます。「未来を欲する限り私たちに可能性が尽きることはない」です。