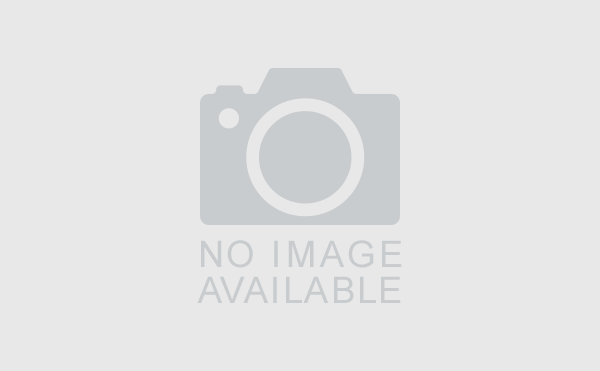裏側との接続の難しさ
やはり、フィールドワークは大切ですね
この年末に以前お会いした海の科学館の職員を務める方のお仕事を観にFWに行きました。一人で行こうか迷いましたが、コロナ禍で自発的に発足したResarteはあまりこういったFWを皆でできていなかったので多少無理を言ってメンバーにも同行してもらいました。今回は「海」という自然を相手にするので、博物館のみだけではなく、周りの環境も十分に肌で感じるため前泊しました。忙しい中ありがとう!今回のFWで考えたことを2つにまとめます。
1に学芸員的な働き方をしていて、研究もしながら高い熱量で来館者に魅力を伝えることを重視している人はいることを目の当たりにできました。贅沢なことに博物館への訪問前夜夕食を共にし、じっくりとお話を伺いました。私たちのチームが大学に所属している「研究者」よりも、博物館・科学館・美術館などの社会教育施設に所属する、学芸員や研究員を中心に活動をシフトした際にその背景を調べたりインタビューをしてきました。その集大成として今回じっくりお話をし親睦を深められたのではないかと思います。新たな社会的に意義のある研究をしようとする姿勢と、博物館を訪れる人への「魅力の伝達」への想いがとても高い熱量で私たちもモチベーションが上がりました。現状では社会教育施設に足を運んでもなかなかじっくりと職員の方にお話をお伺いするのが難しかったり、その魅力を知らないという場合もあるので、私たちの活動によってより多くの人の間に入れるのではないかと思っています。この問題意識は2に繋がるものです。
2に、実際に博物館を見学して、博物館の持つ理想的なリソースの活用と伝達の難しさを感じました。展示の意図は、千葉県の海の環境に関する展示と、実際に海辺で観察したくなるような海の生き物の展示があり、実際にFWへ繋げて欲しいという意図を持ったものでした。発展的な解説プリントも子供用、大人用どちらも準備さてていて、簡潔にポイントが記されていてとてもわかりやすかったです。一方で博物館の便りに掲載されている来館者から届いた声を見るとなかなかその意図はただ展示を見るだけでは伝わりづらいこともわかりました。一定のリテラシーが求められると表現できるでしょう。展示を自分なりの興味のアンテナを張ることや、問いと向き合わないと、せっかくの展示も単なる情報の羅列になってしまいます。また博物館の存在意義として、展示だけではなく資料の収集や保存、それに伴う学術的な研究があるわけですが、その活動についてはなかなか伝わりづらい部分もあるのだろうと思います。今回見学した博物館はバックヤードツアーなどを行っているそうで、とても有効だなと感じました。活動のキーワードである「学びや好奇心への入り口」を広義の「アート」で作れているのではないかと思います。しかし、とても職員さんの多忙さは想像に難くないので私たちのような民間の活動や事業としてこういった課題に対して何かしらできることがあるのではないかという思いを強くしました。
最後に個人的に心を動かされたのは近くに漂着したクジラを見たことと、海中公園で魚を見たことでした。なんとなく詩にしたのでよければ読んでください。
クジラだった君の葬式
泣き声がする。見下ろすと死体。別の何者かが鳴いている。 ザトウクジラが逝った。 安心しろ。そこのカラスがきっと還してくれる。 哺乳類の居場所はどこだろう。海から来たのであれば海に帰るべきなのか。 でも、最期は陸にという場合もある。 だからこうして君に出会えたね。 1個体である君の葬式名はMegaptera novaeangliae 場所は35°07'54.2"N 140°16'38.3"E 期間はとても長くなるだろう ただ見るだけという変わった参列をする私は途中で来て途中で帰る 遺体の供養と送り出しは隣種に任せよう 泳ぐことの大半は波に身を任せることである 行ったり来たりゆらりゆらりと 僕は最期にどこにたどり着くか君に聞いてみよう