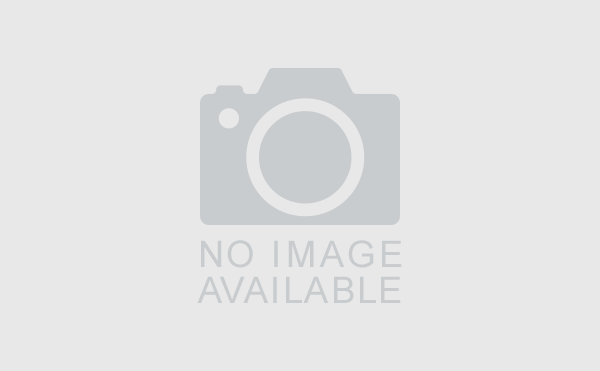「人」・「言葉」で伝える
新しいことを知る・学ぶ時に、どのように出逢ったのか、出会う方法によってその物事に対する印象や興味の度合いが変わった経験はありませんか?例えば、学校の授業で面白い/好きな先生に数学を教わったら、数学を好きになった経験等、ないでしょうか?
少なくとも筆者はこれを経験したうちの一人だと思います(笑)。意外と私たちの興味はその物事自体に対する判断基準だけでなく、それを知る・学ぶに至った過程も興味の有無を左右する重要な要因なのではないかと思います。本記事では、千葉県立中央博物館分館―海の博物館にて勤務する鳥類研究者の平田和彦氏への訪問を通して、研究や学問に対する人々の興味・関心を促進する上で改めて考えた研究のアウトリーチに関する問題意識について述べます。そしてこれに対して、Resarteが考える研究や学問の発信活動に関する今後の取り組みについて記載していきます。
先ず今回の訪問を通して改めて体感したことは、研究や学問の面白さや奥深さは文章では伝わらないと言うことです。伝わらないと断言してしまうのは、少し行き過ぎな表現かもしれません。しかし、筆者の本音としては、論文や学会誌等、従来研究発信を行う上で用いられてきた「文章」というツールだけでは、その魅力が伝わりきらないという意味です。今回、鳥類研究者の平田氏へのインタビューを通して、筆者は物事を伝える上での「人」、そしてその人から声として発せられる「言葉」の重要さについて考えさせられました。平田氏へのインタビューでは、ポジティブ精神満載でユニークな平田氏の人柄に惹かれ、平田氏が話す研究やそれに関連する様々なお話一つ一つに対して、筆者自身ワクワクしながら終始耳を傾けていました。研究や学問を知る上で、研究に携わっている研究者がどのような姿勢で研究に日々向き合っているのか、研究者が発する言葉一つ一つと彼らのユニークな人柄や個性が相まることで、研究全体の新たな魅力として人々の研究や学問に対する興味・関心が促進するのではないかと感じました。研究や学問はそこに携わる研究者があってこそ成り立つものであるからこそ、研究者自身の「人」としての魅力は研究や学問に対して抱く受け手の印象やイメージに大きく影響を及ぼす重要な要因であると考えます。研究や学問を今後社会に向けて発信していく上で、当事者である研究者が彼らの言葉でまだ知られざる魅力や面白さを公に自ら伝えていくことは、一種の伝達方法として文章以上の計り知れない価値があるのではないでしょうか。
これを踏まえ、Resarteでは研究者や学問に携わる方々が公に発信し、人々が新しい研究や学問に気軽に触れ合うことができる機会を創出する取り組みを更に行っていきたいと考えております。現在このような対外向けの研究のアウトリーチ活動は限られているからこそ、私たちのような団体が少しずつ活動機会を広げていくことで、研究や学問について新たな方法や視点から触れ合うことを体験する機会を提供したいと考えております。活動を行う上で、Resarteは美術的な視点(アート)を交え、非言語的な観点から研究や学問との接点を創造することで、文章という従来の発信方法に捉われない新たな出会いを試みています。今月1月8日にResarteとしては初のアートワークショップイベントを設け、アートと研究・学問を融合させる方向性で人々の研究や学問への興味・関心をアートの側面からどのように影響を及ぼすことが出来るのか、仮説検証として行います。Resarteが挑む様々なチャレンジに今後も是非注目していただければ幸いです。